
東京スカイツリーで、宇宙へのワクワクが広がる特別なイベントが始まります。2025年8月1日から11日まで、千葉工業大学が主催する「楽しんだもんがち宇宙展」では、見て、触れて、学べる宇宙体験が誰でも無料で楽しめます。
注目は、火星のまわりにある2つの月を調べるために計画されている、日本の最新探査機「MMX(Martian Moons eXploration)」の模型展示。その大きさは実物のおよそ半分。世界で初めて“火星の月の砂を持ち帰る”ことを目指す挑戦の姿が、会場でリアルに体感できます。
さらに期間中には、実際にその探査プロジェクトに関わる研究者が登場し、子どもでもわかるような言葉で解説してくれる特別トークも実施。宇宙や科学がぐっと身近になる貴重な機会です。
難しい知識がなくても大丈夫。ふらっと立ち寄って、未来を感じる体験ができる——そんな“夏休みの宇宙旅”が、東京スカイツリーで待っています。
宇宙に一歩近づく夏休みの体験イベント

東京スカイツリーの8階にある千葉工業大学のキャンパスで、家族連れにも人気の体験型イベントが開催されます。会期は2025年8月1日から11日までの11日間。「楽しんだもんがち宇宙展」と題されたこの催しは、宇宙や化学の世界を楽しく学べる展示や体験コンテンツがそろった、夏休みにぴったりの企画です。
主催は、宇宙探査研究を行う千葉工業大学 惑星探査研究センター(PERC)。会場には、宇宙空間をバーチャルで体験できるVRコンテンツや、参加型のワークショップも用意されており、子どもから大人まで夢中になれる内容が詰まっています。専門知識がなくても気軽に楽しめるため、自由研究のヒントにもなりそうです。
会場は東京ソラマチ®8階の特設会場で、入場は無料。申し込みも不要で、ふらっと立ち寄ってそのまま参加できる点も魅力のひとつです。
見るだけじゃない!学べる「楽しんだもんがち宇宙展」
このイベントが特別なのは、ただ展示を見るだけではなく、実際に「体験できる」工夫がたくさんあることです。会場では、宇宙空間をリアルに感じられるVRコンテンツや、科学の楽しさを実感できるワークショップなど、誰でも自由に参加できるプログラムが展開されます。
子どもたちにとっては、夏休みの自由研究や好奇心をくすぐるきっかけに。大人にとっても、普段なかなか触れることのない宇宙開発や先端技術を身近に感じられる絶好のチャンスです。
イベント全体を通じて伝えたいメッセージは、「楽しい世界は、楽しむ人がつくりだす」ということ。未来を切り開く技術や学びが、どこか遠くではなく、すぐ近くにある——そんなことを感じさせてくれる空間になっています。 イベントの雰囲気をもっと知りたい方は、公式の紹介映像もおすすめです。
火星の月を目指す探査機MMXとは?

「MMX(Martian Moons eXploration)」は、日本の宇宙機関JAXAが進めている火星衛星探査計画です。その目的は、火星のまわりを回っている2つの小さな月、フォボスとダイモスの正体を調べること。2026年の打ち上げを目指し、世界で初めて“火星の月の砂を地球に持ち帰る”という挑戦が進んでいます。
今回のイベントでは、このMMX探査機の1/2スケール模型が特別に展示されます。実際の大きさの半分とはいえ、十分な迫力があり、探査機がどのように作られているのかを目の前で見ることができます。普段は映像や図でしか見ることのない探査機を、実物に近い形でじっくり観察できるのは貴重な体験です。
展示は、8月2日から11日まで、東京ソラマチ®8階の「惑星探査エリア」で行われます。こちらも入場無料、予約不要で誰でも見ることができます。火星や宇宙に少しでも興味がある人なら、きっと引き込まれる内容です。
宇宙の最前線を知る特別解説トーク
MMX探査機の1/2スケール模型が展示されるだけでなく、宇宙展の期間中には実際にこのプロジェクトに携わっている研究者たちが登壇し、解説トークを行う日も設けられています。開催は8月6日から8日までの3日間。1日3回、30分ずつの短いトークセッションが予定されており、申込不要・無料で誰でも参加できます。
それぞれの登壇者は、探査機の開発や運用において重要なパートを担うキーパーソン。日ごとに異なるテーマで語られる解説は、専門的でありながらも、一般の人にもわかりやすく噛み砕かれた内容になっており、宇宙探査がどのように進められているのかをリアルに感じられる機会です。
和田浩二さん ― MMXの「着陸地点」を決める責任者

8月6日に登壇するのは、千葉工業大学 惑星探査研究センター副所長の和田浩二さん。MMX探査機が着陸する地点を選ぶ「着陸地点選定ワーキングチーム」の責任者として活躍されています。
安全に探査機を着陸させるためには、重力や地形、障害物の有無などを慎重に見極める必要があります。和田さんは、天体衝突のシミュレーションや数値解析を使って着地点を絞り込む、まさに“宇宙のナビゲーター”的存在です。これまでにも「はやぶさ2」の衝突装置などに関わってきた実績があり、今回の解説でも、宇宙探査の裏側にある精密な計算や判断の世界を教えてくれます。
千秋博紀さん ― 宇宙での「高さ」を測るレーザ高度計を担当

8月7日に登壇するのは、同じく副所長の千秋博紀さん。MMX探査機に搭載される「レーザ高度計(LIDAR)」の開発責任者であり、探査機が地表からどれくらいの距離にいるのかを測る、いわば“宇宙でのメジャー”をつくる専門家です。
過去には「はやぶさ2」のレーザ高度計や赤外線カメラのチームにも参加しており、宇宙機器開発の現場で数々のプロジェクトに関わってきました。宇宙空間ではGPSのような位置情報が使えないため、こうした機器が探査機の“目”として大きな役割を果たします。講演では、地上とは異なる測定の難しさや工夫についても語られる予定です。
小林正規さん ― 宇宙のチリを捉える「ダストカウンター」の開発者
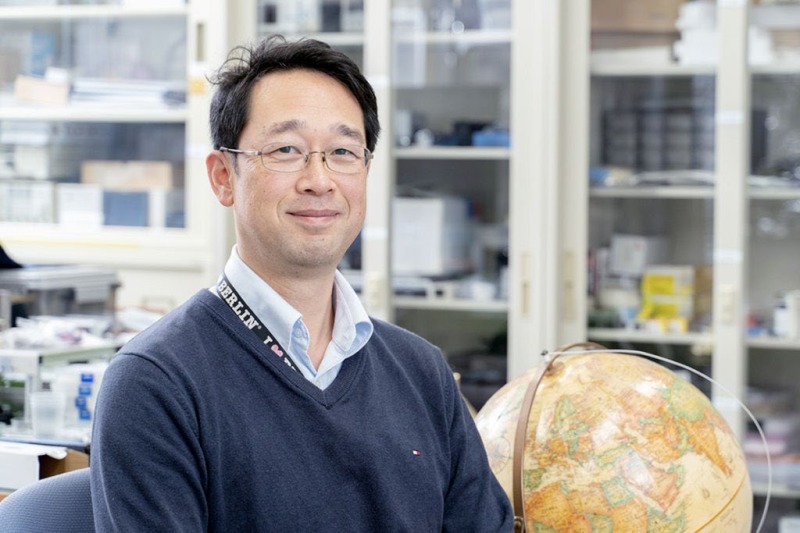
8月8日に登壇するのは、小林正規さん。MMX探査機に搭載される「ダストカウンター(CMDM)」という機器の開発を担当しています。この装置は、宇宙空間に漂う小さな粒子(ダスト)をとらえて記録するもので、火星の月の周囲にある環境を知る手がかりとなる重要なデータを集めます。
小林さんは、これまでにも木星探査機「JUICE」や水星探査機「BepiColombo」、彗星探査機「Rosetta」など、数々の国際的な宇宙ミッションに参加。宇宙を飛ぶ“観測の目”を手がけてきた、まさに宇宙機器開発のエキスパートです。
宇宙と未来を支える企業と大学の力
今回の宇宙展を支えているのは、産業と研究の最前線を走る2つの存在です。ひとつは、電子機器に使われる素材「ソルダーレジスト」で世界トップシェアを誇る太陽ホールディングス株式会社。化学の力でさまざまな分野を支える同社は、科学や未来への関心を育てる活動にも力を入れており、今回のイベントにも特別協賛として参加しています。
もうひとつは、会場でもある千葉工業大学 惑星探査研究センター(PERC)。JAXAやNASAとも連携しながら、宇宙の起源や惑星の進化を研究している本格的な探査機関です。MMXの観測機器開発にも深く関わっており、最先端の研究が身近に感じられる貴重な機会となっています。
企業と大学、2つの力がタッグを組むことで、「知ることの楽しさ」と「未来を考えるきっかけ」が形になった今回のイベント。会場で目にする展示や体験の背景には、こうした本気のものづくりと探究心が詰まっています。
宇宙の入口は、意外と近くにあるかも?
東京スカイツリーというおなじみのランドマークで、最先端の宇宙探査や研究者の生の声に触れられる今回のイベントは、宇宙を遠い世界の話ではなく「自分ごと」として感じさせてくれます。模型に目を奪われ、研究者の話に耳を傾けるうちに、私たちの日常も科学とつながっていることに気づくはずです。入場も参加も無料、予約も不要。暑い夏の日のちょっとした寄り道が、未来を考える大きなきっかけになるかもしれません。








