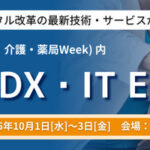教室の後ろでは、まるで祭りの太鼓が打ち鳴らされたかのようにざわめきが広がりました。見慣れた4年生の教室に、突然持ち込まれたのは伝統ある町の喧騒、担ぎ手の声、水しぶき――ただし、それらは“現地”ではなく、スクリーン越しの体験でした。福岡市立弥永西小学校で実施されたこの授業では、子どもたちが普段目にする机と黒板の空間から一歩も出ることなく、地域のお祭りである 博多祇園山笠 の“中”に入ったかのようなデジタル体験を味わいました。
この“出前授業”を手がけた 株式会社ごきげんコーポレーション(GGC)は、教室という身近な場を使って、移動や時間の制約を抱える児童にも本物の「体験」を届けることを目指していました。では、この試みは実際どのように実現され、どんな反応を生んだのでしょうか。そして、それを支えた技術「実写VR」とは何だったのか。この記事では、第三者の視点からその全貌を明らかにしていきたいと思います。
出前授業がつなぐ、学校と地域文化の新しい接点

福岡市立弥永西小学校の4年生を対象に、株式会社ごきげんコーポレーション(GGC)による“瞬間移動体験”の出前授業が行われました。目的は、福岡市の伝統行事である博多祇園山笠を、児童の多くが実体験したことがない現状を受け、「行きたい」という意欲を高める機会とするためです。実際、体験前のアンケートではクラス約9割が「行ったことがない」と回答していました。
授業は、冒頭に「これから山笠に行きます」という呼びかけからスタート。児童たちはVRゴーグルを装着し、祭りの動き・音・水しぶきといった360度映像に包まれて、教室という場を超えた体験をしました。映像の最中、児童からは「えっ!スゴい!」「目の前で走っとる!」「水かけられた!」といった声があがりました。
体験後には7割以上が「行きたい!」と、さらに1割程度が「参加したい!」と回答。さらに注目すべきは、VRゴーグルを使った体験が児童にとってほぼ初めてであったにもかかわらず、「重たい」「酔った」との声が聞かれなかったという点です。
こうした出前体験授業は、移動や時間・費用などの制約を抱える学校に対して、教室内で非日常体験を提供し、「知らない」「行ったことがない」を「興味ある」「行ってみたい」に変える契機となりました。
移動を超える体験がつくる、学びの新しい入口

今回の授業から読み取れる大きな意義のひとつは、児童の意識変化です。体験前には実際に行ったことがない割合が高かったものが、短時間のVR体験を通じて、「行きたい」という具体的な興味に変化しました。これは、実体験に近い感覚を教室内で提供できたことの証と言えます。
また、出前体験という形式自体の強みも明らかです。学校の枠内で地域文化・祭りを“体験”できることで、校外学習や現地訪問で生じやすいハードルを軽減できます。さらに、地域の伝統や文化に触れる入口としても活用できる可能性があります。
一方で、課題も存在します。今回の実施は1校・1クラスでの試行という規模で、持続的・広域展開のためには、機材・教員支援・運用体制などの整備が不可欠です。また、児童の「行きたい」を次の行動や学びに結びつけるフォローアップも今後の鍵となるでしょう。技術面でも、機材の準備・安全配慮・操作慣れなど、運用上の検討点があります。
“本物”を映し出すVR 実写型ならではの没入感

「実写VR」とは、360度カメラ等で現実の風景や出来事を撮影し、その映像をゴーグル等で体験できる没入型の形式を指します。従来のCG空間型VRとは異なり、実際の場にいるかのようなリアルな映像体験が特徴です。
この仕組みにより、視界・音響・動きが連動した体験が可能となり、「その場に居る」感覚が増します。教育や体験学習の場では、アクセスが難しい現場(祭り・文化財・工場など)を教室に呼び込む手段として注目されています。
ただし、実写VRには撮影・編集・視聴環境など制作・運用面での挑戦も伴います。視点移動・音響・長時間体験による酔い対策など、体験の質を保つには工夫が必要です。本授業のように、児童約70名が体験してネガティブな反応が出なかったという報告は、実写VRの運用可能性を示す実践例と言えます。
子どもたちの好奇心は、どこまで旅していくのか
GGCは今回の出前授業を皮切りに、実写VRによる“瞬間移動体験”を多数の子どもたちに提供していく意向を示しています。福岡市内では中高校生向けの事業も動き出しており、地域外に向けた展開も視野に入れているようです。
教室という身近な場で体験の扉を開くこの試みは、子どもたちが地域文化への関心を持つきっかけになる可能性があります。とはいえ、今後の拡大にあたっては運用体制・教員支援・機材整備など、関係者の連携と仕組み作りが重要です。
今回の出前体験授業は、教室という日常空間で技術を通じて“行きたい気持ち”を引き出す一つのモデルといえるでしょう。今後、このような体験型プログラムがどのように広がり、子どもたちの学びや地域の魅力発信にどう貢献していくか、注目しておきたいです。