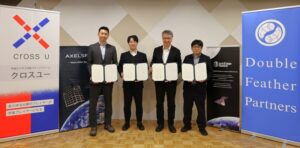建設業界と聞くと、「人手不足」「現場は大変そう」「デジタル化が遅れている」といったイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。一方で、実際の現場では、こうした課題を少しずつ変えようとする動きが静かに進んでいます。
その一つが、建設分野にデジタル技術を取り入れる「建設DX」と呼ばれる取り組みです。書類作業のオンライン化や、遠隔での現場確認、ドローンを使った点検など、これまで当たり前だった仕事のやり方を見直す試みが各地で始まっています。
2025年秋、建設業界に関わる企業や行政、研究者などが集まり、こうした取り組みを共有し合う場が設けられました。現場の課題にどう向き合い、デジタル技術をどのように活かしていくのか。難しい専門論ではなく、実際の事例や考え方を通じて語られた点が印象的です。
この記事では、建設DXを取り巻く現在地と、業界内でどのような変化が起きているのかを整理します。建設業界に詳しくない人でも、なぜ今DXが求められているのか、その背景が見えてくる内容です。
建設DXが求められる背景と、業界が直面している課題

建設業界では近年、現場を取り巻く環境が大きく変わりつつあります。少子高齢化による人手不足に加え、建物やインフラの老朽化が進み、限られた人員でより多くの業務をこなす必要が出てきました。現場では安全への配慮が欠かせず、確認作業や書類対応にも多くの時間が割かれています。
こうした状況の中で注目されているのが、デジタル技術を活用して業務の進め方そのものを見直す「建設DX」です。単なる作業の効率化ではなく、現場の負担を減らし、持続的に仕事を続けられる環境を整えることが求められています。
今回の交流の場でも、建設分野における生産性向上が重要なテーマとして扱われました。建築に関わる手続きや確認作業は長年アナログな方法が主流でしたが、今後は、オンライン化やデータ活用を前提とした仕組みへ移行していく流れが示されています。これにより、現場に足を運ばなくても確認できる作業が増え、移動や待ち時間の削減につながる可能性があります。
また、建設の現場は天候や立地条件に左右されやすく、危険を伴う作業も少なくありません。人の経験や勘に頼る部分が大きい一方で、その技術を次の世代にどう引き継ぐかも課題となっています。デジタル技術やAIの活用は、こうした技能の共有や標準化を支える手段としても期待されています。
建設DXは、一部の先進的な企業だけの取り組みではなく、国や自治体を含めた業界全体の課題として捉えられています。今回の取り組みからは、建設の仕事をより安全で続けやすいものにしていくために、デジタルの力をどう活かすかが真剣に議論されている様子がうかがえます。
国と大手建設会社が示した建設DXの方向性

建設DXを考えるうえで欠かせないのが、制度をつくる側と、実際に現場を動かす側の視点です。今回の取り組みでは、国の方針と大手建設会社の考え方がそれぞれ示され、建設DXがどこへ向かおうとしているのかが浮かび上がりました。
国の立場からは、建築分野における手続きや確認作業を、デジタル前提の仕組みへと移行していく方向性が示されています。図面や書類を紙でやり取りするのではなく、データとして扱うことで、確認のスピードや正確性を高めていく考え方です。将来的には、建築に関わる行政手続き全体がオンラインで完結することを見据えた動きも進められています。
こうした制度面の変化は、単に便利になるという話にとどまりません。人手不足が続く中で、限られた人数でも業務を回せる体制をつくることや、確認作業にかかる時間を減らし、本来注力すべき業務に集中できる環境を整えることにつながります。建設DXは、現場だけでなく、業界全体の構造を支える取り組みとして位置づけられています。
一方で、大手建設会社の視点から語られたのは、DXは上から押し付けるものではなく、現場から育っていくものだという考え方です。デジタル技術やAIを導入すること自体が目的ではなく、それを使う人や現場の「場」がどう変わるかが重要だとされています。
特に印象的なのは、DXを「仲間づくり」と捉える考え方です。自社だけで完結させるのではなく、スタートアップ企業や協力会社と信頼関係を築きながら、新しい仕組みを共につくっていく。その過程で、これまで属人的だった技能やノウハウを共有し、次の世代へつないでいくことが目指されています。
国が示す制度の方向性と、現場から生まれる工夫や試み。この両方がかみ合うことで、建設DXは単なるデジタル化ではなく、働き方そのものを見直す動きとして広がっていくように感じられます。
自治体とテック企業が取り組む、現場DXの具体例

建設DXが現場でどのように形になっているのかを知るうえで、自治体とテック企業の協力事例は分かりやすいヒントになります。今回紹介された取り組みは、いずれも「現場の困りごと」から出発している点が共通しています。
神奈川県藤沢市では、公共建築物の改修や維持管理の需要が高まる一方で、人手不足という課題を抱えていました。そこで、施工管理の進め方そのものを見直し、デジタルを活用した管理手法を取り入れています。これにより、現場に足を運ばなくても状況を確認できる場面が増え、移動時間の削減や確認作業の効率化につながっているとされています。自治体内部での連携も進み、これまで個別に行われていた検査や確認作業を整理する動きも見られます。
千葉県千葉市の事例では、下水道管の点検という、特に危険を伴いやすい作業が取り上げられました。下水道の点検は、流れが速い場所や常に水がたまっている箇所もあり、人が直接入って確認することが難しいケースがあります。こうした環境の中で、ドローンを活用した点検手法が検討され、安全性と効率の両立を目指した取り組みが進められています。
これらの事例に共通しているのは、「最新技術を使うこと」そのものが目的ではない点です。現場で何が課題になっているのかを整理し、それに対して無理のない形でデジタル技術を組み合わせていることが分かります。また、自治体とテック企業が一方的な関係ではなく、対話を重ねながら進めている点も特徴的です。
建設DXは、特別な現場だけで成立するものではありません。日々の業務の中にある小さな負担やリスクをどう減らすか。その積み重ねが、結果として現場の安全性や働きやすさを高めていく取り組みにつながっていることが、具体例を通して見えてきます。
建設DXが示す、これからの建設のかたち
今回の取り組みから見えてくるのは、建設DXが単なるデジタル化や新技術の導入ではないという点です。人手不足や安全性の確保、業務の効率化といった現場の課題に対し、国、自治体、企業がそれぞれの立場から向き合い、少しずつ形を変えようとしています。
印象的なのは、制度の整備と現場の工夫が並行して進められていることです。行政手続きのデジタル化やデータ活用の仕組みづくりは、現場の負担を減らすための土台となります。一方で、実際の現場では、人や環境に合わせた柔軟な取り組みが積み重ねられています。どちらか一方だけでは成り立たず、両者が連動することで建設DXは現実的なものになっていきます。
また、自治体とテック企業、建設会社が協力し合う姿からは、DXが「関係づくり」の側面を持っていることも感じられます。新しい技術をどう使うかだけでなく、誰と、どのように進めていくか。そのプロセス自体が、これからの建設業界にとって重要なテーマになっていくはずです。
建設業界の話ではありますが、ここで示された考え方は、他の分野にも通じるものがあります。現場の声を起点にしながら、デジタルの力を無理なく取り入れていく。その積み重ねが、働き方や業界のあり方を少しずつ変えていくのではないでしょうか。
派手な変化ではなく、着実な一歩として進む建設DX。その動きはすでに始まっており、今後どのように広がっていくのか、引き続き注目されます。